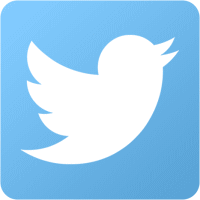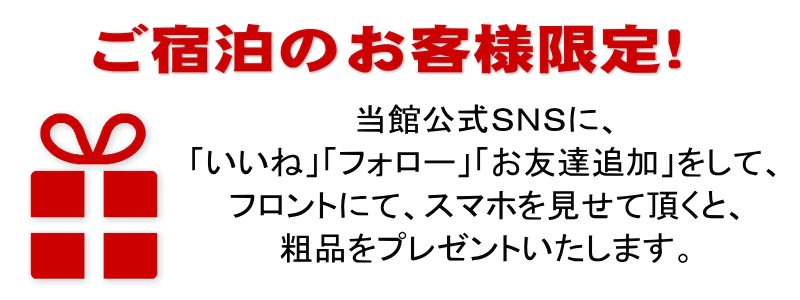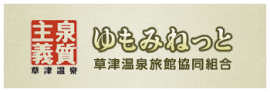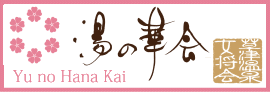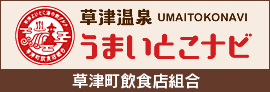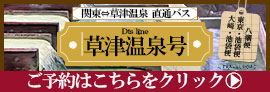クロマネノキ(黒豆の木)です。
ツツジ科スノキ属の落葉低木です。
こちらは、まだ当ブログの草津温泉花図鑑で紹介しておりませんでしたので、ご紹介させて頂きます。
殺生河原の小殺生に咲いているハクサンシャクナゲを見に行った時に咲いているのを見つけました。
白い釣鐘の様な可愛らしい小さい花を咲かせております。
秋になると葉は紅葉し、黒い豆の様な果実をつけます。
だから、黒豆の木と言うのでしょうか。

味は、ブルーベリーの様な甘酸っぱい味だそうです。
今、火山の噴火警戒レベルにより本白根山の方へは行く事が出来ませんが、殺生河原から温泉街まで行くハイキングコースで十分にお楽しみ頂けます。
是非、お出かけくださいませ。