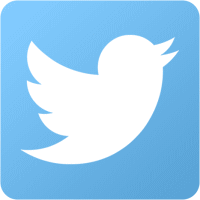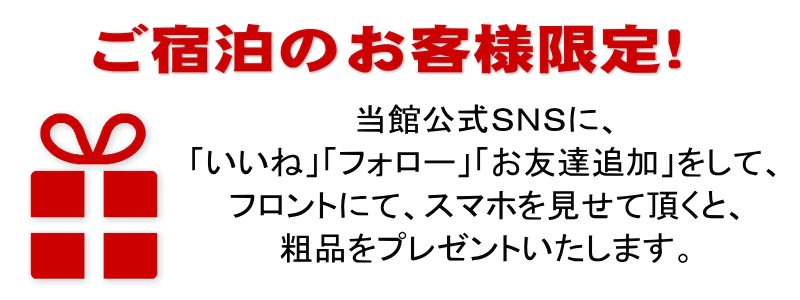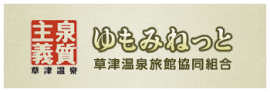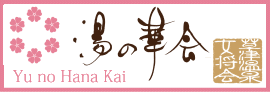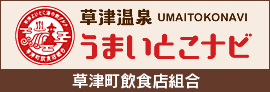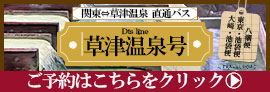キツネノボタン(狐の牡丹)の花です。
草津温泉で咲いているのは、この変異種でヤマキツネボタンとも呼ばれている様です。
別名コペイトウグサやウマゼリとも呼ばれております。
草津森の癒し歩道のサイクリングコース、ロイヤルコースでいっぱい咲いてました。
この名前が分かるまでは、結構苦労しました。
もし、間違っていたら申し訳ございません。
iphoneの花しらべアプリでは、キツネノボタンとケキツネノボタンが候補で表示されました。
他にも、調べてみますと、ヤマキツネノボタンという種類もありました。

ケキツネノボタンは、この果実の尖がった先がまっすぐなのに対して、
キツネノボタンは先が曲がっているとの事です。
これは明らかに曲がっているで間違いないかと思いました。

ところがケキツネノボタンの茎に毛がたくさんあるのが特徴との事でしたが、
この花には毛がたくさんありました。
ここで、非常に悩みました。
キツネノボタンの変異種で、比較的毛の多く、
山地で咲く花をヤマキツネボタンというのもありました。
草津温泉の花図鑑ガイドにも、ヤマキツネノボタンという名前を見つけました。
そこで、ブログのタイトルをヤマキツネボタンとしようと思いました。
しかし、これは、キツネノボタンに含まれ、
最近では区別しない方向で進められているとの事で、
この花の名前を最新植物情報として、キツネのボタンとしました。
また、3枚の葉が重なるのもキツネノボタンの特徴な様です。

こちら、草津森癒しの歩道サイクリングコースで撮影でしたものです。
この花は、毒があります。
キンポウゲ属の植物にはラヌンクリンという有毒成分が含まれており、
誤って食べてしまうと口腔内や消化器に炎症を起こし、茎葉の汁が皮膚につくとかぶれるそうです。
昔、草津味料理と言って山野草を食べた事がありますが、良く知っておかないと怖いですね。
毒のあるもの、嫌なものは、昔からキツネに例えられ、
葉の形が牡丹の葉に似ているところから、狐の牡丹(キツネノボアタン)という名前が付けられた様です。
もし、草津癒しの森歩道を散策中にこの花を見つけましたら、
こういう名前の花が咲いているんだなと知って頂ければ幸いです。