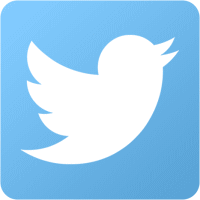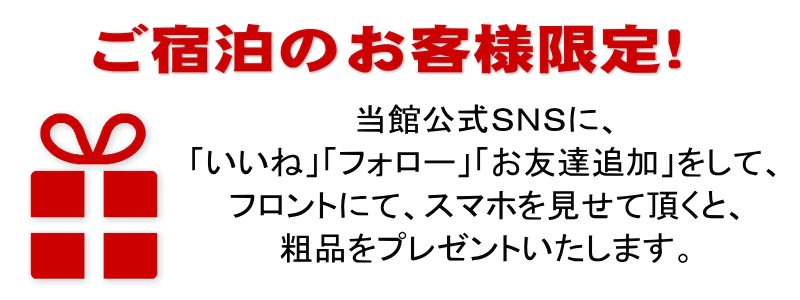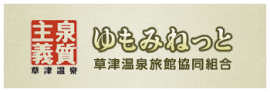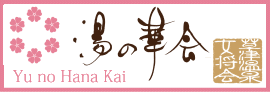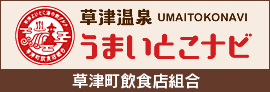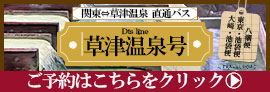自宅から草津まで、国道292号線を通って通勤して、
あまりにも、当たり前の様に、たくさん咲いている花を
見過ごしておりました。
5月下旬頃からでしょうか、
結構、長い期間に渡り、今もたくさん咲いております。

これを見て、私は、ずっと、
「マーガレットが咲いている」と、心の中で思っておりました。
普通の花?
でも、良く調べてみると、これは「フランスギク」という
名前の花である事が分かりました。

フランスギク(仏蘭西菊)は、ヨ-ロッパ原産で
江戸末期頃に観賞用に持ち込まれ、
寒さに強く、冬を越せる事と、その強い繁殖力で
野生化したそうです。
このフランスギクの特徴は、暑さに弱いそうです。
高温多湿が、大の苦手です。
涼しい 草津温泉ならではの咲いている花だったんですね。
それを初めて知ったので、
こちらの花図鑑に掲載させて頂きました。
●マーガレット、シャスターデージと、フランスギクの違いについて
ちなみに、マーガレットはこちらです。

ウィィペディアより
本当に、似てますよね。
マーガレットとの大きな違いは、葉の形です。
こちらが、フランスギクの葉です。
フランスギクは、フランスギク属。

こちらが、マーガレットの葉です。
マーガレットは、和名で木春菊。
モクシュンギク属の花です。

明らかに、葉の形がちがいますね。
マーガレットは、カナリア諸島原産の花で、
暖かい土地で育つ花です。
草津温泉の様な寒い冬を越して、
野生化する事は、ありえないそうです。
あと、シャスターデージーと言う、似た花があります。
これは、観賞用に改良された、フランスギクとハマギクを交配種です。
シャスターデージーは、フランスギクより茎がしっかりしていて、
上を向いて花を咲かせます。

この類の花は、頭状花序(とうじょうかじょ)と言って、
多数の花が集まって、ひとつの花の形を作るものです。
只今、国道292号線沿いで、車で走っていると、
誰もが目にすると思います。
特に、草津温泉に入ると多く咲いてます。
是非、ご覧ください。